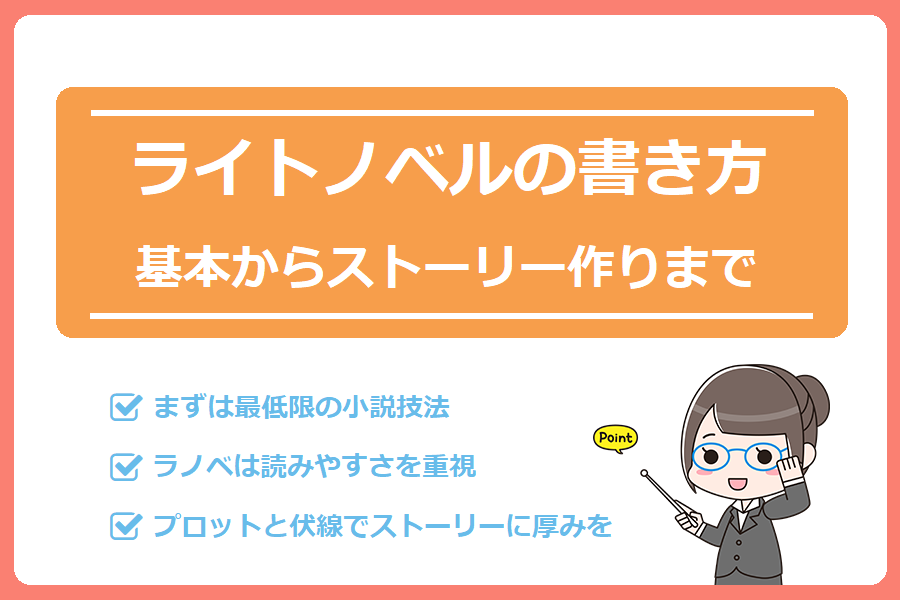
・読みやすさも重視
・プロットと伏線でストーリーに厚みを
小説、ライトノベルを書くとなった時に、最初にぶつかるのが「小説の書き方」ですよね。
結論から言ってしまうと、「面白ければなんでもあり」で表現方法は進化していくものだと思うのですが、なんだかんだで最低限の文章作法は必要です。
最低限が無いと、最初の数行で読むのを止められてしまいますからね。
これは一般小説の方が強い傾向ですが、ライトノベルでも同様なので、最低限の書き方をぜひ覚えておいてください。
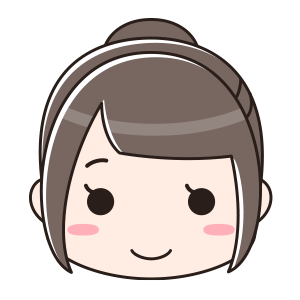

目次
ライトノベル小説の書き方
ライトノベルも一般小説も、書き方は基本的に同じなのですが、好まれる書き方が少し違うことは覚えておいた方がいいです。
この違いによって、一般小説に慣れた作家さんが、ライトノベルでのヒット作を出しにくいという落とし穴があるんですね。
コツは、「基本の書き方を押さえたうえでわかりやすく書く」ということです。
描写をあえて簡易化することに抵抗があるかもしれませんが、ライトノベルの需要は描写の味わい深さではありません。読みやすさと爽快感が最重要です。
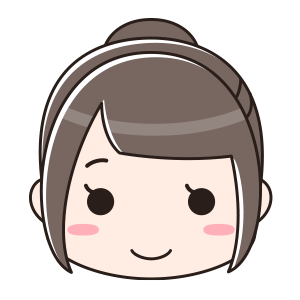

文章作法・守るべきルール(初心者用)
まずは、小説を書く上での文章作法・守るべきルールを箇条書きしておきます。掘り下げは後からやっていきましょう。
【文章作法・守るべきルール】
- セリフは「」で囲う
- 段落始めは一字下げる
- 「……」(三点リーダー)と「――」(ダッシュ)は二つ続ける
- 疑問符と感嘆符(「?」や「!」)の後は一マス空ける
- 顔文字を使わない
- 人称を意識する
まず押さえておかなければならないのはこの辺りです。おそらく、これがひとつでもできていないと1ページ目での脱落案件となってしまいます。
これらはライトノベルだけに限らず、小説全般の書き方に通じるルールです。ぜひ覚えておいてください。
書籍化の際は、正しい文章作法に校正しなければなりませんし、ネット小説サイトでの投稿もぜひこの基本を意識してみてください。
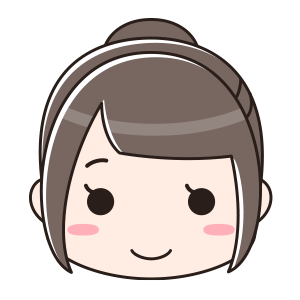

セリフは「」で囲う
セリフを「」で囲うのは、あまりに一般的なので問題ないでしょう。
どんどんと横に並べるのではなく、セリフごとに改行して使ってください。
変則的な使い方としては、『』の使い方でしょうか。
『』は重要単語を囲ったり、セリフ中のセリフ説明に使ったりします。回想や思念やマイクアナウンスで使うのもいいでしょう。
(例文)
_何だこの声は。どこから聞こえている。
_母の言葉を思い出す。
こんな感じでしょうか。
「」『』の使い方は、それなりに読書をされる方ならばそこまで問題ないと思います。
段落始めは一字下げ
段落の始めは一字下げるのが基本なのですが、これが案外忘れがちかもしれません。
特に、小説家になろうを始めとしたネット小説を見ていると、基本を学ばずに投稿されている方も多いので、段落下げがなされていないケースが多く見受けられます。
これは見やすさにおいて重要なウエイトを占めるので、ぜひ意識してみてください。
注意点としては、セリフの「」は一字下げしないということです。
(例文)
_夕食はなんだったか尋ねる。
「パンだよ。パン」
「ああ、そうだったね」
_こうして夜食の準備を始めた。
文章内容がひどいですが、字下げ例としてはこんな感じですね。
これは短文なので実感しにくいかもしれませんが、一文が二行に渡る場合だと字下げ効果が出て、文の起点がわかりやすくなります。
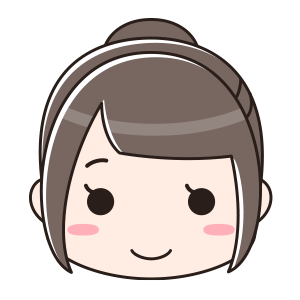

「……」と「――」は二つ続ける
「……」と「――」は、二つ続けて使用してください。
これ、意外に忘れられがちなのですが、基本のひとつでもあるので要チェックです。
「…」は間の取り方、「―」は瞬間や時間の流れで使うことが多いですが、これはそれぞれの使い方を模索するのがいいでしょう。
二つで足りない場合は、四つ連続で使ってください。偶数セットで使うことを覚えておくといいと思います。
疑問符と感嘆符の後は一マス空ける
疑問符「?」と疑問符「!」の後は一マス空けてください。これも見やすさのためです。
例外として、「!」か「?」が続く場合と、会話文の最後が「!」か「?」で終わる場合は一マス空けません。
(例文)
「待ちやがれ! 絶対に許さん!!」
「はあ!?」
_ちょっと待てよ?
こんな感じです。
疑問符と感嘆符の連続使用の是非もまたあるんですけどね。ライトノベルだと、連続使用はかなり多い印象です。
顔文字を使わない
文章に顔文字を入れると感情表現がしやすいのですが、これは一般文芸では使いません。
文章で感情を表現するのが醍醐味でもあるので、顔文字の使用はしないのが基本です。
(笑)や(泣)なんかも安っぽくなるのでやめておきましょう。ギャグとしてあえて使うのはありかもしれませんが、個人的にはNGかなと思っています。
ここまでの注意点は、ライトノベルにおいても基本なのでぜひマスターしてください。と言ってもそんなに難しいことではありませんから、すぐに身に着くはずです。
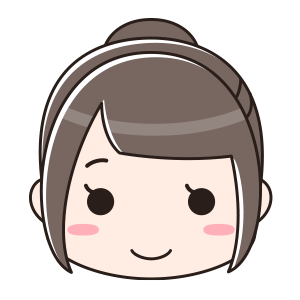

一人称・三人称

続いて、地の文の書き方。一人称と三人称です。
これは覚えておきたい基本でもあるのですが、少しハードルが高くなるので、徐々に身に着けていくことになるでしょう。
人称の違いは、誰視点で地の文(セリフ以外の文)を書くかということになります。
一人称は自分視点、三人称は俯瞰からの神視点という違いで、心理とカメラの位置がどこにあるかということを意識してください。
主人公=佐藤という例文でいきます。
その時、僕は小説が楽しいと思った。
(三人称)
その時、佐藤は小説が楽しいと思った。
痛い。俺の指から血が流れる。
(三人称)
佐藤の指から血が流れ、痛そうな表情を見せる。
俺と佐々木は走った。見上げると太陽が眩しかったが、流れる汗が心地よい。
(三人称)
二人の男が走っていた。照りつける太陽が輝いているが、その流れる汗は心地よさそうだ。
こんな感じでしょうか。人称の例文は難しいですね。
一人称は感情表現が伝わりやすいのに対して、三人称は客観的な描写がしやすいメリットがあります。
どちらを選ぶかは好みでもありますが、重要なのは視点をころころと変えないということです。
一人称視点だったのに、いつの間にか三人称になっていると読者は混乱してしまいます。書く方は整理できているかもしれませんが、読者側に無駄なストレスを与えてはいけません。
一人称視点が移り変わるのは、区切りがあればまだいいでしょう。これもできるだけ避けるべきではありますが。
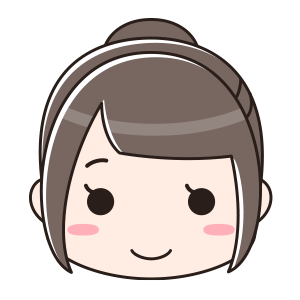

小説文章力を上げるポイント
ライトノベル・小説の書き方の基本に続いて、文章力も上げていかなければなりません。
これがまた難しいんですけどね。ある程度のコツはあるので意識してみてください。
- 数字表記
- 記号の使い方
- 改行
- 語尾のリズム
- 擬音の使い方
- 「てにをは」の使い方
- 「の」の連続をさける
- 読む時に書くことを意識する
描写や表現方法のパターンを増やすことも重要ですが、とりあえずはこの辺りから始めてみましょう。
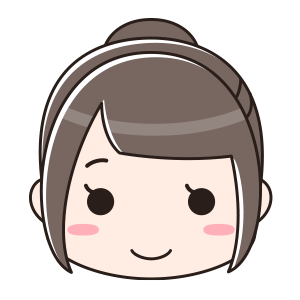

数字表記
一般小説だけではなく、ライトノベルを書く際に、意外と悩ましいのが数字表記です。
ステータスなんかもそうですし、やたらと数字の出番が多いんですよね。
数字表記のパターンとしては、漢数字・半角数字・全角数字ですが、これはケースバイケースとなり、一概にこれというものはありません。
「二つのリンゴと、3つのみかん」
これは違和感がありますね。どちらかに統一しましょう。
基本的には漢数字が無難かなと思います。次に全角数字で、半角数字は二桁のみの使用がいいでしょう。
これは、ネット小説サイトが横書きなのに対して、書籍が縦書きだからです。
漢数字だと基本的に違和感がなく、全角数字だと縦書きでも数字がそのまま並びます。しかし、半角数字は縦書きだと90度回転してしまうデメリットがあるんですね。
ライトノベルだとステータス表記することもあり、数字の使い方は個人的にも正解はないかなと思っています。それぞれのスタイルに合ったものを使ってみてください。
・一桁の数字は基本的に漢数字
・キリのいい10や100や200は、十や百や二百で漢数字表記
・キリの悪い257のような数字は、二百五十七や二五七よりも全角数字表記
・年号や日付の2018年1月1日は、二〇一八年一月一日の漢数字表記もあり
逆に、間違えやすいケースも挙げておきます。
| 正しい | 間違い |
|---|---|
| 数十人 | 数10人 |
| 数百万円 | 数100万円 |
| 何百人 | 何100人 |
| 幾千年 | 幾1000年 |
数、何、幾などが付く場合は、漢数字表記と覚えておくといいでしょう。
ちなみに、小数点は「・」(ナカグロ)を使ってください。「3・14159」という感じですね。
記号の使い方
一般小説はもちろん、ライトノベルでも記号は使います。
主に使う記号は、感嘆符、疑問符、「」『』、-、…、ですね。これらは上記までに使い方を書いたので省きます。
「・」(ナカグロ)は名前や列挙などで使います。
()は補足や思考内容で使うことが多いです。
《》(二重ギュメ)はルビ振りに使うので、文章中に使うことは少ないでしょう。
【】(墨つきパーレン)は、名称の囲みに使われますが、あまり使わない方がいいのかなとも感じます。『』を使う方がいいのではないでしょうか。
/(スラッシュ)、*(アスタリスク)、※(こめじるし)、~(なみがた)辺りも割と見かけますが、あまり好ましくはない記号に感じます。これらはできれば文章で表現したいところですね。
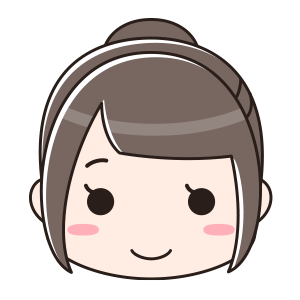

ライトノベルは読みやすさ重視で改行を

ライトノベルというか、ネットで小説を公開する際は改行が重要となります。特に一行空けですね。
限られたスペースの書籍では字詰めになるのですが、ネット小説(特にスマホ表示)だと改行のあるなしで見やすさが全く違います。
改行の仕方に正解はないのですが、一般的な使い方を挙げてみます。
- セリフの連続は一行空けない
- 意味が繋がっているなら改行せずに続ける
- 場面転換しないなら改行のみで一行空けない
- 地の文の区切りで一行空ける
こんな感じでしょうか。
この辺りは千差万別で、改行ごとに一行開けたり、場面転換で二行空けを使う方もいらっしゃいます。
スマホ表示に特化した短文を意識して、一文ごとに改行を入れる方もいるでしょう。
ただ、あまりに改行が多いと安っぽく見えてしまいますし、書籍化の際には苦労するものと思われます。ある程度は、書籍フォーマットを意識してみてください(書籍化だけが目的ではないと思いますが)。
ただ、書籍フォーマットを意識しすぎて改行頻度が少ないと、一画面が真っ黒になってしまい、それだけで読む気を無くしてしまう場合も見受けられます。
パッと見の圧迫感を避け、文章のリズムも重視して改行を使っていきましょう。
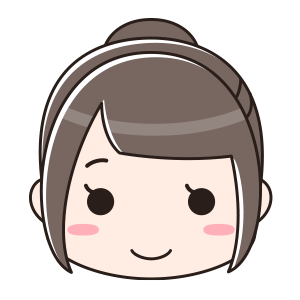

語尾のリズム
語尾のリズムの書き方について悩まれている方が意外に多いようです。
特に、「~た」「~だ」で文章が終わってしまう傾向があると聞きました。
しかしこれは同じ内容でも、少し表現方法を変えるだけで解決する問題でもあるんですよね。
体言止めや倒置法を使ってみるのもおすすめです。
では、例文をいってみましょう。
↓
俺に書けることがあるならば頑張らないわけがない。
↓
それがラノベの分岐点にもなるだろう。
↓
その書き方で問題はない。今のところは。
↓
その時、俺の本を捨てたのは加藤。
意味合いや強調したいところが変わる場合もあるので注意ですが、似た意味合いでも語尾を変えることはできるという例です。語尾にお悩みの方はこの辺りを意識してみるといいかもしれません。
擬音の使い方
ライトノベルと言えば、擬音の激しさという面もあるでしょう。
ただ、擬音や叫び声を使うほどに安っぽくなることを覚えておいた方がいいかもしれません。
ライトノベルでは使われまくる擬音も、一般小説ではほとんど使われません。
「うおおおお!!」
という叫び声が聞こえる。
↓
轟音と共に爆発音が響き渡り、何者かの咆哮が続いた。
怪物は唸り声をあげている。
↓
地の底から響くような唸り声をあげる怪物。
例文としてはこんな感じでしょうか。
音を描写で表現するのは小説の醍醐味でもあるので、擬音とのバランスを意識してみてください。
ルビを振る
わかりにくい漢字にはルビを振りましょう。
それぞれのサイトで使い方は違うかと思いますが、《》で囲むとルビが振れることが多いです。そして部分ルビは|《》で指定します。
「てにをは」の使い方
小説の書き方だけではありませんが、「てにをは」を正しく使うことは小説の文法として特に重要です。
多少なら問題ありませんが、ひどいと意味そのものが変わってしまいます。
「それがいいです」と「それでいいです」だと要望か妥協かのニュアンスが違いますよね。
「これはおいしい」と「これがおいしい」だと、前者は他のものを否定していますし、後者だとそれを強く肯定しています(前後の文脈次第ではまたニュアンスが変わってきますが)。
こういった微妙なニュアンスが変わってくるので、小説を書く際は「てにをは」をしっかりと意識していきましょう。
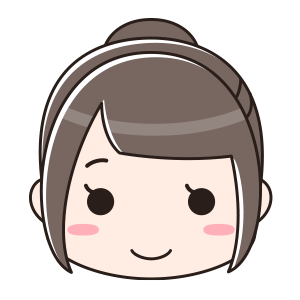

「の」の連続使用を避ける
「の」使っちゃいますよね。私も意識していないと、「の」が連続してしまうことがあります。
「俺の隣の女の髪の色は赤だった」
これだと意味は通じないことも無いですが、リズムが非常に悪く読みにくいですよね。これを改善する方法はたくさんありますが、いくつか挙げてみましょう。
「俺の隣の女。その髪色は赤だった」
「俺の隣にいる女。その髪色は赤だった」
「俺の隣。その女の髪色は赤だった」
「俺が隣の女に目をやると、その髪色は赤だった」
とまあ色々とありますが、「の」を減らす方法はたくさんあります。ぜひ書き方のパターンを意識してみてください。
読む時に書くことを意識する
「小説を読む時に、自分が書くことを意識する」
これが文章力を上げる一番のコツです。アウトプットを前提としたインプットは強いんですね。
意識していると、参考となる描写や表現方法が数多く出てくるはずで、それらを参考にしていくといい文章が書ける土台が築かれていきます。
あくまでも参考ですよ。パクリはいけません。参考とリスペクトです。
ラノベでは難しい表現を使わない

一般小説とライトノベルの大きな違いとして、特に意識するべきは「読みやすさ」です。
ライトノベルでは描写そのものよりも、キャラや設定やストーリーを気軽に楽しんでもらえることを意識して書きましょう。
かと言って、安っぽくならないようなバランスも重要で、「難しい表現をわざわざ使わない」ということを意識するのがおすすめです。
例えば、「正鵠」ってわかりますか?
正鵠は、物事の要点や核心という意味なのですが、これを素でわかる方は少数派ではないでしょうか。
これなら普通に「核心」とした方がいいですし、こういった難しい表現を使わないだけで読みやすさはグッと上がります。
作家側と読者側の知識の差があると考え、できるだけわかりやすい表現で読者ニーズに合ったバランスに仕上げましょう。高校生くらいが読みやすい文章を意識するといいかもしれません。
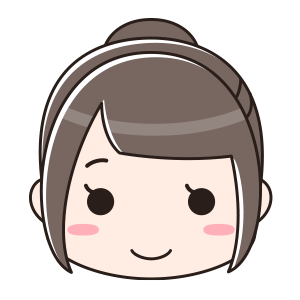

推敲する
文章が書けたら、読み直して手を加えてください。推敲です。
一発で完璧な文章が書けるのがベストなんですけどね。それを常に達成するのはほぼ不可能です。見直す癖をつけましょう。
コツは「正しく、わかりやすい」ことです。
【推敲ポイント】
- 誤字脱字チェック
誤字脱字は論外ですので、すぐに直してください。 - 言い回しと表現を変える
言い回しと表現は、もっといい表現はないか、付近の文と重ねっていないか等をチェックしながら改善してみましょう。 - 並び替える
前後の単語や文章の並び替えによる改善も有効です。 - 削る
余計な単語や文は削りましょう。読みやすさにおいて、引き算が重要になってきます。
推敲の際は、この辺りを意識してみましょう。
読み直すことでわかる違和感があるはずです。ぜひ推敲してみてください。
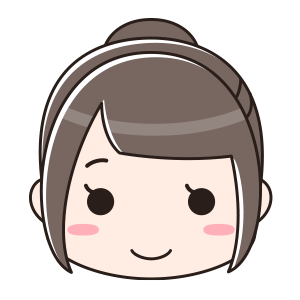

ラノベストーリーの作り方

ライトノベル小説の書き方として、初心者用の基本文法、文章力向上と来ましたが、最後にストーリーの作り方です。
面白い物語というのは全てを凌駕する面があるので、これさえ極めれば書き方や技法なんてどうでもいいという感じもしちゃうんですけどね。
ただ、これが最難関と言ってもいいでしょう。
世界観、設定、キャラ、ストーリー、これらをイチから作り上げ(最近はテンプレものがあるので楽ですが)、プロットを組んで伏線を張る。言ってしまえばこれだけですが、これが全ての作家さんを悩ませる種もあります。
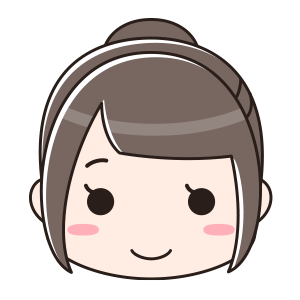

世界観の構築
ストーリー作りのために、まずは世界観の構築です。
ファンタジー世界なのか、現実世界なのか、異世界なのか、未来なのか。様々ですが、この舞台設定が根幹となります。
ラノベだと、中世ヨーロッパの文化背景でのファンタジーが圧倒的に多く、受け入れられやすいです。これはゲームの影響もあるでしょう。
描写も「中世ヨーロッパの街並み」で通じるので非常に楽でもありますし、おすすめの世界設定のひとつです。
そして、そこにどんな国があるのか、武器は何か、魔法なのか異能力なのかという設定を練っていきます。
逆算もいいですね。剣や魔法を主軸としたいのなら現代よりも異世界ですし、現代兵器が苦手なら過去や異世界を選ぶ方がいいでしょう。
世界設定

国々があれば、そこには様々な思惑があります。
仲の良い国、悪い国。平和な国もあれば腐敗した国もあるでしょう。
国をいくつか設定して、それぞれに特色を持たせると世界に色が着き始めます。
まあ、この辺りは恋愛ラブコメかファンタジーバトルかで大きく変わる部分でもありますよね。
それぞれのジャンルの書き方はこちらをご参考ください。
キャラ設定

物語を盛り上げるには、キャラ設定が最も重要と言っていいかもしれません。
これはライトノベルや小説だけではなく、漫画にも共通していて、「ストーリーではなくキャラを書け」とも言われるぐらいです。
キャラとしては大きく分けて、主人公、仲間、敵ですね。
真面目な主人公か、陽気な主人公か、陰がある主人公か。これが最も根幹となります。
主人公の成長を描くということを前提としてみてください。強さでも精神面でも境遇でもなんでもいいです。成長することでカタルシスの得やすい流れができあがります。
仲間と敵キャラ
仲間は、ヒロインを主軸として、様々な役割があります。主人公を引き立てるだけではなく、できるだけ生きたキャラを作ってください。
特に「何が目的なのか」を設定しないとキャラがブレます。これは主要キャラにはしっかり設定してください。物語に厚みも出ます。
ライバルの存在もいいですね。敵とするのか、仲間のひとりなのか。
敵は、純粋な悪なのか、訳ありなのか、人間なのか、魔物なのか等々様々ですが、これらは世界の謎にも絡めることができるので、ボスの境遇と思想を設定するぐらいでちょうどいいと思います。
敵キャラに魅力が無いと、物語は盛り上がりません(バトルもの以外なら、仲間たちとのやり取りだけで魅せる方法もありますが)。
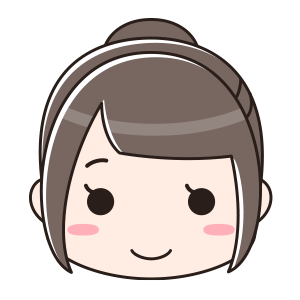

プロットと伏線
世界観とキャラが決まれば、物語を書き始めることができます。
しかし、最初からある程度のストーリーの道筋は作っておきましょう。プロットですね。
料理で例えるなら、レシピがプロット、隠し味が伏線、具材が世界観、調味料がキャラといったところでしょうか。
プロットなしで書くこともできますが、物語の質を上げるためには伏線を入れておくことが重要です。
プロットの書き方
プロットの書き方は、人それぞれ千差万別ですが、基本的には物語の流れとシーンの列挙です。
- 主人公が森で記憶喪失
- ヒロインに発見される
- 街で謎の集団と戦う
- 倒してヒロインと結ばれる
こんな感じでシンプルですが、とりあえずのストーリーとはなりますよね。ここに味付けをしていくことになります。
- 主人公はなぜ記憶喪失なのか?
- ヒロインと謎の集団の関係は?
- 謎の集団の目的は?
これらによって、ラストの達成感は全く違うものになるでしょう。
そして設計図があることで、プロットを広げていくことも容易になります。
街で酒場に入る。
謎の集団の黒幕と戦う。
等々、様々な広げ方がありますよね。
プロットなしで物語を書いていくと、行き当たりばったりの単調な物語となってしまいますし、何よりも伏線が入れにくいことがデメリットとなってしまいます。
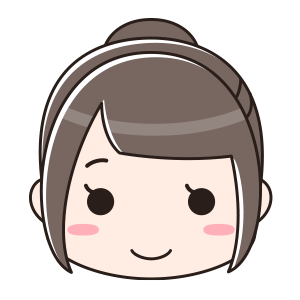

伏線の入れ方
プロットを書いておくと、ラストに向けての流れがあるので、伏線が入れやすくなります。
- ラストのボスを倒すためのヒントを序盤で仕込んでおく。
- 出会った仲間が、謎の集団の一人で実は敵だった。
- ラストに出てくる助っ人の人影を森で差し込んでおく。
- 主人公を助けるヒロインの秘めた力を匂わせておく。
等々、後に繋がる要素を小出しに仕込んでおくことができます。
「あの時のあれはここで繋がるのか」という快感は、伏線ありきのストーリーものの醍醐味ですよね。
あえてミスリードするのもアリだと思いますし、伏線を絡めて物語の達成感を上げていってください。
ライトノベル小説の書き方まとめ
ライトノベルを中心として小説の書き方でした。
上達のためにはとにかく書いて、そして意識することが重要です。
文章作法から、文章力の向上、ストーリーの作り方まで様々ですが、基本を押さえて徐々に上達していきましょう。

・文章作法の基本を押さえる
・読みやすく爽快なストーリーを
・魅力的なキャラを作る



















